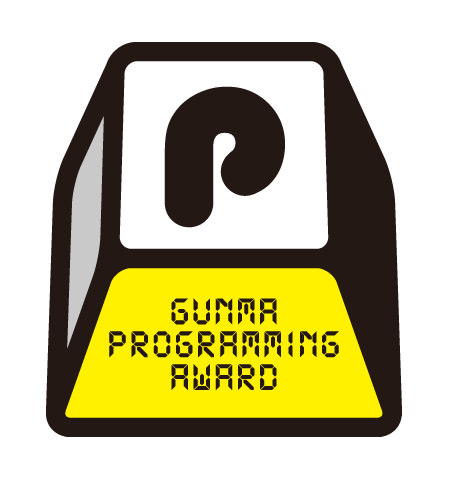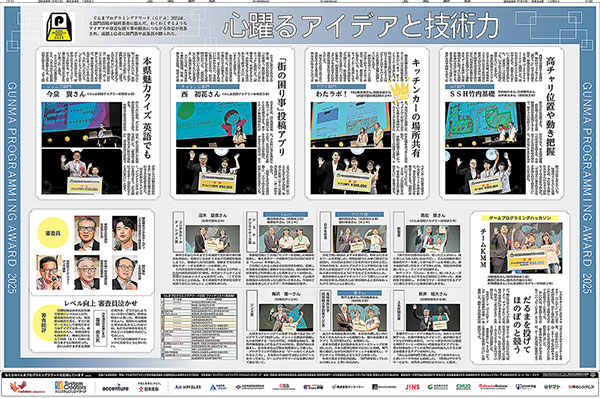
PDFをダウンロード
ぐんまプログラミングアワード(GPA)2025は、4部門20組が最終審査に臨んだ。わくわくするようなアイデアや身近な困り事の解決につながる作品が発表され、成績上位者に部門賞や企業賞が贈られた。
【IoT部門】
SSH竹内基礎
竹内桜介さん、久保晃市さん 山本佑斗さん(高崎高2年)
◎高チャリ位置や動き把握
高崎市が運営する登録不要、無料のシェアサイクル「高チャリ」の不正利用を防ぎ、管理を効率化するIoT機器「Takachalink」を開発した。決められた利用エリアや時間が守られず、放置されるといった課題の解決を目指した。「受賞は一つの目標だった。いろんな人の協力に感謝したい」と喜んだ。
衛星利用測位システム(GPS)を活用。自転車がエリア外に出ると利用者に音声で知らせるほか、管理者に情報を送る機能を持たせた。利用者の位置や動きが分かる管理アプリと連動させ、データを集計し目撃情報のみに頼っていた放置自転車の回収に役立てる。走る場所によって指定した音声を流す機能もあり、広告などにも活用できる。
長距離でも対応できる無線通信技術を採用することで、高チャリの利用エリアだけでなく、市全域の管理への活用を見据える。今後は子どもや高齢者の見守り、防災などさまざまな分野での応用も考えている。
物理のコンテストに出場するため、やむなく欠場した久保さんの分まで頑張り、2人で栄光をつかんだ。「今後は市に働きかけるなど実現に向けて動きたい」と力を込めた。
【アプリ部門】=MVP=
わたラボ!
村山真奈美さん、加藤衣遥さん(共愛学園前橋国際大3年)
◎キッチンカーの場所共有
固定店舗を持たないキッチンカーの出店情報を提供するアプリ「 R● Kitchen」を考案した。今回、初出場で部門賞に加え、MVPを受賞した2人は「たくさんのアドバイスをくれた教授や先輩に感謝している」と話す。
県内各地のイベント会場では多くのキッチンカーが並び、利用者、事業者ともに増えている。ところが、キッチンカーを利用しようと思ってSNSや情報誌などで調べても、出店情報を得ることは難しい。その点に着目し、利用者が複数のメディアをまたがずに出店場所の情報を共有できるようにした。
雨などの天候不良で急に出店を中止する場合は、通知を受け取ることができる。お気に入りに登録したキッチンカーが近くに出店している場合も通知が入り、タイミングを逃さずに好きな物を食べることが可能だ。
移動式店舗では難しかった口コミの機能も追加。キッチンカーの店舗で提供されるQRコードを読み取り、書き込みする仕組みを構築することで、信頼性の高い口コミにした。
2人は「この経験を生かし、将来はIT系の仕事に就きたい」と笑顔で語る。
編注:●はアポストロフィの’s
【チャレンジ部門】
西 初花さん(ぐんま国際アカデミー中等部3年)
◎「街の困り事」投稿アプリ
カラスに荒らされたごみ捨て場、街灯が切れ暗くなった夜道―。街の困り事を投稿するアプリ「ぐんけんチェック」を開発した。「課題を共有、可視化することで、行政任せでなく地域のみんなで解決したい」とまちづくりの理想をかなえる一手として提案する。
自身の気付きが開発の契機となった。近所のごみ捨て場にカラスが集まってしまうが、どこに連絡すればいいか分からない。市役所に電話したものの、担当の部署までたどり着くには時間がかかった。「地域の課題に気付いた人が連絡をしないのはもったいなさ過ぎる」と開発に乗り出した。
アプリでは、利用者は困り事の位置情報、写真、分類などを投稿。地図上に表示するため、同じ問題意識を持つユーザーが複数いることを可視化できる。ボランティア募集機能も付けた。ごみ拾いなどを想定しており、住民の自主的な動きを促すことが可能だ。
プログラム制作は、思うようにアプリが作動しないことも多く苦しんだが、生成人工知能(AI)に改善点を相談し、一歩一歩作り込んだ。
「投稿するだけで地域が動く」。アプリのさらなる改善に意欲を見せている。
【ジュニア部門】
今泉 翼さん(ぐんま国際アカデミー初等部4年)
◎本県魅力クイズ 英語でも
群馬の魅力を多くの人に知ってもらいたいと、本県に関するクイズゲームをプログラミングで制作した。部門賞を獲得し、「頑張ってここまでたどり着けたことがうれしい」と喜んだ。
家族で伊香保温泉(渋川市)を訪れた時に、ポーランドから旅行に来た家族と親しくなったのがきっかけだ。遠方の国まで日本の文化が広まっているのを知り、うれしかったという。「インターネットの普及でグローバル社会になり、世界の人たちとコミュニケーションが取れる。ゲームを通じ群馬県の魅力を伝えたいと思った」と語る。
クイズは三つの難易度ごとに、○×方式や3択問題が各30問出題される。うち10問正解すると、より上級のレベルに進め、デジタルの合格証をもらうことができる。
問題文と解答は日本語のほか、自らが翻訳した英語で表記した。「群馬県で面積が最も小さい町は大泉町か」「草津温泉には年間でどのくらいの観光客が訪れるか」など本県の魅力が伝わるような問題を集めた。
将来の夢はプログラマー。プログラミングは「思いを表現できて、人を笑顔にできるゲームが作れるところが面白い」と話す。
【コシダカホールディングス賞】
沼木 碧泉さん(茗溪学園高3年)
中学2年から今年まで5年連続で文化祭の実行委員を務めた。毎年生じる会計ミスなどの課題を解消しようと、準備から当日の運営、精算まで文化祭全般をサポートする専用ツールを開発した。
6月の文化祭で実際に使うと、昨年は3万円あった会計誤差が5000円に激減。注文がリアルタイムで厨房(ちゅうぼう)に伝わるシステムも好評だった。「ITだからできることがある。多くの高校や大学の文化祭で実現できたらうれしい」と受賞を喜んだ。
【システムクリエイターズ賞】
Lovox
渡辺志音さん(前橋高2年) 塚原壮平さん(同1年)
自動販売機とごみ箱にセンサーを搭載した機器を設置し、購入者のデータ収集やごみの分別に役立てる「Lovox」を考案した。
ごみ箱に入れると商品や分別方法を検知。収集した情報を自販機と連動させる仕組み。商品提案や分別支援など利用者に合った音声コメントが流れる。
学校でごみが分別されていない現状や、ごみ箱や自販機が人格を持ったら面白いと考えた。今後はごみ収集を通じたビッグデータの構築を目指す。
【日本生命賞】
めだか組
岩村亮汰さん(太田旭小4年) 岩村幸音さん(同1年)
自宅で飼い始めたメダカを題材に、卵をふ化させるゲームを開発した。時間が経つと水中に卵やごみが現れ、川が汚れる前にごみを片付けて卵をふ化して得点を競う。おおたプログラミング学校に通う亮汰さんが家族のアイデアを得ながら制作。メダカの泳ぐ速さが変わるようにするなど工夫を凝らした。
妹の幸音さんはデジタルペイントで愛らしいメダカの絵を担当。亮汰さんは「賞が取れると思わなかったのでうれしい」と喜んだ。
【群電賞】
高松慧さん(ぐんま国際アカデミー初等部5年)
「食べ方を注意されるが、習ったことがない。僕と同じような人がいるはずだ」。そんな経験を基に食事のマナーを楽しく学べるゲームを考案した。箸や食器の使い方をクイズで学んだ後、写真の中の間違いをシューティングで指摘する。
制作ソフト「Unity」を使い、狙いをスムーズに動かせるようにするなど細部にこだわった。食事の様子を撮影し、その場でマナーを判定できるアプリに進化させたいと構想を膨らませる。
【ジンズ賞】
梅沢陽一さん(前橋笂井小2年)
大好きなクレーンゲームを家でも遊べるようにプログラミングで制作した。クレーンと景品が接触したかを判断する「当たり判定」の範囲を狭めて、獲得の難易度を上げるなど工夫が光る。景品の絵は手描きし、自ら吹き込んだ歌を効果音として使った。
プログラミングの面白さは「ゲームをたくさん作れるところ」。3年前から始めて100以上のゲームを作ってきた。ゲームプログラマーになる夢に向けて進んでいく。
【高崎商科大学・同短期大学部賞(TUC賞)】
君子es
森戸士雄さん、竹渕遙希さん(高崎高2年)
友人から相談を受けた際、本当は応援したいのにうまく伝えられなかった経験から、誰かを応援するアプリ「LISTENAVI」を開発した。
相手を応援する対話法を学ぶワークショップに参加したが、スキル習得は簡単ではないと実感。専門家に相談しながら対話のテクニックを数値化し、リアルタイムで可視化するシステムを作った。
昨年に続き2回目の挑戦。「部門賞を狙っていたから悔しい」と思いを込めた。
【上毛新聞社賞】
新井結大さん (前橋桂萱東小6年)
◆ゲームプログラミングハッカソン◆
チームKMM
◎だるまを投げてほのぼのと競う
8種のゲーム・アプリ集を作った。おみくじや計算ゲーム、自身が得意なタイピング、絵が描けるアプリなど内容も多彩だ。コーヒー好きの父には温度と時間でコーヒーの味わいの変化を示すアプリを、日々料理を作ってくれる母には材料を入力すると献立を提案するアプリを制作した。
「みんなが短時間で楽しめるアプリを作りたい」と長いコード作成にも挑戦した。「将来はプログラマーになり、世界の人の役に立ちたい」と話す。
ツルをモチーフにしたキャラクター「ツルグン」が下仁田ネギの剣を持ち、次々と現れる敵にだるまを投げて攻略までのタイムを競うゲームを作った。
珍しいのは、敵を倒すのではなく「ハッピーにする」ところだ。敵に見立てたイチゴや佐野ラーメン、ギョーザといった他県の名産品にだるまを当てると、相手は「ありがとう」と笑顔になる。
今回のテーマ「ウェルビーイング(心身の健康や幸福)」を意識した。鹿野さんが得意の絵でオリジナルキャラクターを考案。「絵がかわいい」(片岡さん)とチームでも好評のキャラクターたちがほのぼのとした雰囲気を醸し出した。
審査員を特にうならせたのが、ゲームの最後に映画のようなエンドロールを付けた点。「制作者やどんな素材を使ったか書きたい」と、以前から自作のゲームにエンドロールを付けている川野さんが提案した。
受賞を果たし、3人は「もっと他の賞にも挑戦したい」と意欲的だった。
◆審査総評◆
福田尚久氏 日本通信社長兼CEO
◎レベル向上 審査員泣かせ
応募総数は前年比34%増で確実にレベルが上がり、審査員泣かせだった。完成度が極めて高く、すぐに新サービスとして発売できそうなアイデアもあった。着想はもちろん、実装段階でも質が高く、開発における人工知能(AI)の使い方のうまさも印象的だった。
若い人がさまざまな課題に気付き、どうにかしようという思いに触れ、将来は明るいと思った。来年挑戦する人へ。周囲からは異端と思われるかもしれないが、私たちが世界を変えてやるという気概を大切にしてほしい。
すべての応募者のチャレンジにおめでとうと言いたい。
◆審査員◆
金井修 コード・フォー・グンマ理事
福田尚久 日本通信社長兼CEO
鈴木維一郎 共同通信社編集局企画委員
腰高理志 コシダカホールディングス執行役員DX推進室長
関口雅弘 上毛新聞社長
掲載日
2025/08/24